投資を目的なくやみくもに始めても、運用を続けていくことは難しいです。
また、投資戦略が適切に立てられず、市場の変動に振り回された結果、資産がマイナスとなって終わる可能性もあります。
着実な資産形成のためにも、投資目的を明確にし、目的に沿った戦略を立てていきましょう!
- 投資目的はなぜ明確にする必要があるのか
- 投資戦略はどのような順序で立てるのか
投資目的の重要性
投資を始める際に、まず最初に取り組むべきことは投資目的を明確にすることです。
つまり「自分はなんのために投資をするのか」ということを考える必要があります。
投資目的を明確にすることは、以下の点において重要です。
- 方向性の確立
- リスク管理の向上
- パフォーマンスの評価

1つずつ解説していくよ!
方向性の確立
投資目的を設定することで、資産運用の方向性がはっきりします。
例えば「老後の生活資金を確保する」という目的を掲げたとします。
この場合、リスクを抑えた運用が必要であり、値動きの安定した資産配分を組まなければいけないと分かります。
投資目的がないと市場の変動に流されがちになりますが、明確な目標を持つことで、長期的な視点で冷静な判断ができるようになります。
リスク管理の向上
投資にはリスクがつきものです。
リスクは運用商品ごとに異なりますが、投資目的を明確にすることで、自分がどれだけのリスクをとれるか判断する基準ができます。

この「自分がどれだけのリスクをとれるか」は「リスク許容度」というよ。
リスク許容度は、年齢や資産状況、ライフステージによって異なります。
若い世代は長期的な投資ができるため、リスクを取って高いリターンを狙うことが可能です。
一方で、リタイア後に向けて資産運用している中高年の方の場合は、リスクを抑えた運用が必要となってきます。
リスク管理の方法についてはこちらの記事にまとめているので、参考にしてみてください。
パフォーマンスの評価
投資目的が明確であれば、その目的に照らし合わせて投資のパフォーマンスを評価することができます。

投資のパフォーマンスとは、利回りだけじゃなくボラティリティ (値動きの幅) も併せて見ていく必要があるよ。
ここで先ほどの「老後の生活資金を確保する」という目的がある場合を考えてみましょう。
目的を明確にしていると、この目的に対してどれだけ近づいているか、またそのプロセスで必要な見直しがあるかを判断しやすくなります。
明確な目的を持つことで、単に利益を追求するのではなく、より計画的な投資が可能となります。
投資戦略の立て方
投資戦略は以下のような手順で立てていきます。
- 目的の明確化
- 目標金額の設定
- 運用期間と積立金額の計算
- リスク許容度の確認
- 運用商品の決定
- 定期的な見直し

各ステップを順番に見ていこう!
目的の明確化
まずはじめに何のために投資を行うのかをはっきりさせましょう。
投資の目的には、以下のようなものが挙げられます。
- 5年後に家を買うための頭金を貯めたい
- 老後に備えて資産を増やしたい
- 子供の教育費を準備したい
投資の目的は、できるだけ具体的に設定することが重要です。
目的が具体的であればあるほど投資戦略を立てやすくなり、その目的に向かってどうすれば良いかが明確になります。
目標金額の設定
投資目的を明確にした後は、目的に応じた具体的な金額を設定します。
例えば「老後の生活資金として4,000万円を用意する」と決めたとしましょう。
この場合、その金額をいつまでに、どのようにして貯めるかという計画が必要です。
目標金額が明確になることで、投資の規模や期間が見えてきます。
また、投資金額やリターンの期待値を計算する際にも、具体的な目標金額があると計画が立てやすくなります。

やみくもにお金を投資に回して、今を楽しむ余裕がなくなったら元も子もないよね…
運用期間と積立額の計算
目標金額が決まったら、それを達成するまでの運用期間と毎月の積立額を考えます。
先ほどの老後資金の例でいうと「30年後の老後の生活資金として4,000万円を用意する」としたとしましょう。
これに想定利回りを追加で設定すると、運用期間と毎月の積立額を試算することができます。
この際重要なのは、想定される利回りを高く設定しすぎないことです。
予想利回りが高すぎると、毎月の積立額を低く設定しすぎて目標金額に到達できない可能性がでてきてしまいます。
リスク許容度の確認
運用商品を選ぶにあたり、自分がどれだけのリスクを許容できるかを考える必要があります。
リスク許容度は、年齢、ライフスタイル、家族構成、収入、支出などの個人の状況に大きく影響されます。

1人1人状況が違うから、各々が自分の現状に向き合って確認していく必要があるよ。
例えば20代の方であれば、リスクを取りながらも長期間にわたって投資を続けることができます。
その場合、株式などリスクの高い商品を選んでも良いでしょう。
一方、リタイアが近い60代の方は、資産を減らさないことが最優先となるため、より安全な投資商品を選ぶことが重要になってきます。
リスク許容度の違いについては、以下の記事で例を出しているので参考にしてみてください。
運用商品の決定
自分のリスク許容度が分かれば、いよいよ運用商品を決めていきます。
運用商品には、主に以下のようなものがあります。
- 投資信託
- 個別株
- 債券
- 不動産
これらの運用商品は1つを選ぶわけではありません。
むしろ複数の商品や資産を組み合わせる、アセットアロケーションの考え方が重要となってきます。
運用商品を決める際には、投資の目的と手段が混同しないようにしましょう。
詳細は以下の記事にまとめていますので、参考にしてみてください。
定期的な見直し
投資目的や計画は、ライフスタイルや経済状況、マーケットの変動など、様々な要因によって見直しが必要になります。

一度決めたら終わり、というわけじゃないよ!
子供の教育費が予想よりも多くかかると分かった場合や、リタイアの時期が早まる場合など、運用を続けていると様々な状況の変化が生じます。
このような状況の変化に応じて、投資の方針や目標を調整していく必要があります。
また、定期的に運用商品のパフォーマンスを確認し、運用計画に対して適切な修正を加えることも大切です。
投資目的を明確にする長期的なメリット
投資目的を明確にし、その目的に基づいて計画的に資産運用を行うことで、以下のような長期的なメリットが期待できます。
- 精神的な安定
- 持続的な資産形成
- 効率的なリソース配分
精神的な安定
投資目的が明確であるため、市場の変動に振り回されず、冷静に対応することができます。
感情に流されずに投資を続けることは、長期運用の成功の鍵です。
持続的な資産形成
明確な目標を持って計画的に投資を行うことで、リスクを適切に管理しながら資産を増やすことが可能になります。
目的がないと短期的な利益に走りがちですが、長期的な視点を持つことで、より着実な資産形成が期待できます。
効率的なリソース配分
投資目的があることで、時間や資金を効率的に配分できます。
無計画な投資はリターンを得られない可能性に繋がります。
目的に合わせて投資を行うことで、複利運用するための時間や元本となる資金をムダにすることを避けられます。
まとめ
投資を成功させるためには、まず明確な目的を設定し、それに基づいて戦略を立てることが不可欠です。
目的が明確であれば、市場の変動に左右されず、冷静に判断を下すことができ、結果として安定した投資成果を追求することができます。
今回紹介した内容を参考にして、自分に合った投資目的を設定し、長期的な資産形成を目指していきましょう。
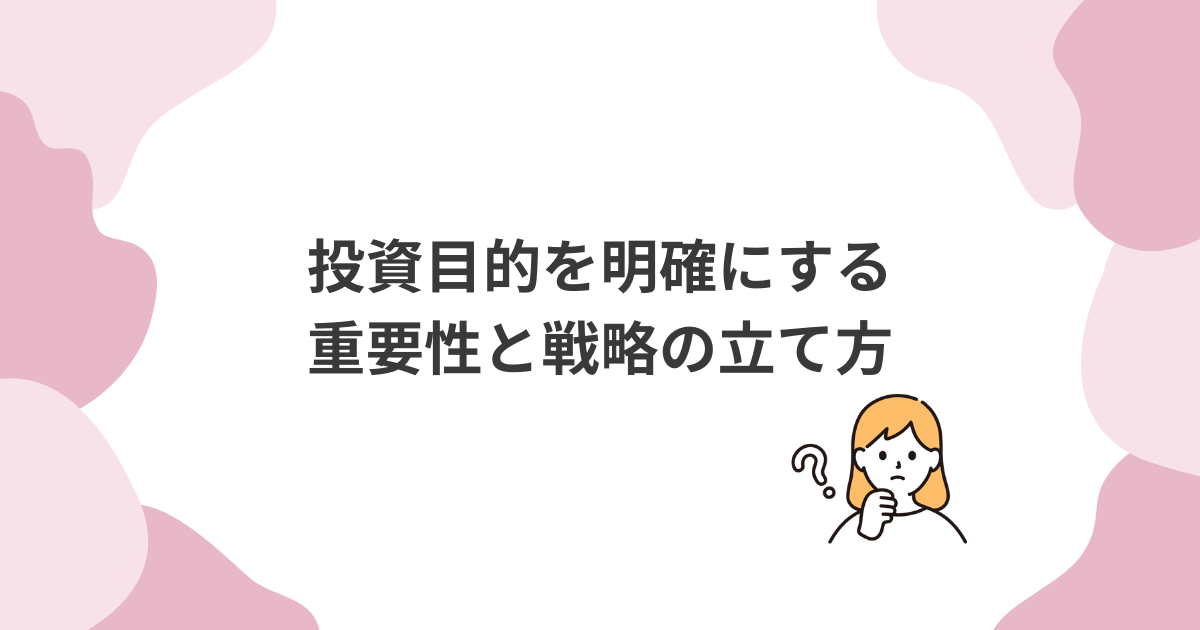
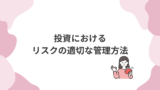
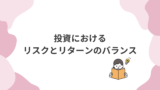

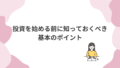
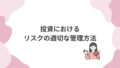
コメント